少年合唱 レーゲンスブルク大聖堂聖歌隊Regensburger Domspatzen ~ テオバルト・シュレムス・メソッド ― 2025年12月24日 02時55分23秒
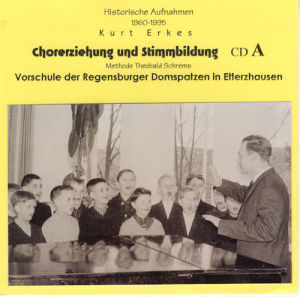
レーゲンスが求めた純粋な響きのために、ビブラートのかからないソプラノは、素朴だけれど、貴重な素材であることを教えてくれます。今回の叔父シュレムスの記録CD、後日の甥シュレムスの演奏会CDと、両シュレムス氏が、レーゲンスにとって、如何に特別で大切な存在で尊敬されていたかがわかります。
とにかく大好きで、昔は、両シュレムス氏の区別さえ頓着せずに「レーゲンス=シュレムス」でレコードを探して聴いて満足していました。現在は、いろいろと便利になって、外国語に疎い私でも資料を読めるようになりました。それが良いんだか、悪いんだか。
ファンである私にとっては、結果としての演奏そのものの輝きが全てで、演奏そのものが大好きなのです。演奏者にとっても、そこだけにスポットライトが当っていて欲しいはず。合唱学校での規律や訓練の厳しさ、指導者のノルマやプレッシャー、ストレスなんてものは、外部には見えなくて良いのです。
ですが、一片の資料から垣間見える、音を作って行く過程から、レーゲンスに限らず、世界中のどこの合唱団を探しても(もしかしてキングスカレッジは別かな?)、それぞれの合唱団の1900年代の魅力には及ばない理由が理解できた気がしました。
私は音楽に関しては好きなだけの素人で、音とかも聞き分けられませんが、演奏から気持ちを読み取るという聴き方をしているので、このCDに収録された曲の中では、「11. レーゲンスブルク大聖堂聖歌隊の元メンバー約200名が、大聖堂音楽監督のためにレクイエムを歌う」が、他の演奏とは違っていて、訴えるものがあったと思います。(by Hetsuji 2025.12.24 WED up)
少年合唱 レーゲンスブルク大聖堂聖歌隊Regensburger Domspatzen ~ 凄みを感じさせるライヴ盤 ― 2025年12月23日 05時42分08秒

少年合唱 モナコ聖カテドラル少年合唱団LES PETITS CHANTEURS DE MONACO ~ 秀逸なソリスト ― 2025年12月20日 23時44分41秒

とにかく、12歳、10歳という若いソリストたちが秀逸。
(by Hetsuji 2025.12.20 sat up)
<Copilot>
[18. サン・ニクラウの鐘]
この曲は、モナコの伝統文化・言語(ムネガスク語)を守る流れの中で歌われている作品のひとつで、「サン・ニコラウの小さな鐘」 という意味を持つタイトルです。モナコでは20世紀に入り、伝統言語を守るために多くの歌や詩が作られました。「U Campanin de San-Niculau」もその文化的流れの中にある作品と考えられます。
*ちなみに大公家はジェノバ貴族の末裔で、モナコの庶民・リグリア系住民の伝統語(ムネガスク語)を護る立場を取っているそうです。
少年合唱 モナコ聖カテドラル少年合唱団LES PETITS CHANTEURS DE MONACO ~ 空気感を伝えるライヴ盤 ― 2025年12月20日 23時40分44秒

目立つソリストはいるのだけれど、演奏について言えば、正直、宗教曲は雑い。(←私の感想も雑すぎるが。Bist du bei mirがあるのにもったいないなー)収録方法に寄るのかもしれない。なので、むしろ、世俗的な後半の曲目以降が聴きやすいかもしれない。聴衆の反応も良くて、演奏を引き立てている。とはいえ、演奏に端正さを残していて意識が崩れていないのはさすが。
中国や韓国の聴衆は、感情表現が情熱的でストレートだなあ、ってたびたび感じる。(by 2025.12.20 sat up)
少年合唱 モナコ聖カテドラル少年合唱団LES PETITS CHANTEURS DE MONACO~豊かな日常が作り出す音 ― 2025年12月18日 22時17分44秒

L'ENFANT ET LA MÉLODIE FRANÇAISE, de la liturgie à la poésie
Direction: Philippe et Pierre DEBAT
1/Tantum ergo - Gabriel Fauré...2'05
2/Ave verum - Gabriel Fauré...3'12
3/Salve Regina - Gabriel Fauré...2'37
4/Maria Mater gratiæ - Gabriel Faure...2'29
5/Ave Maria - Gabriel Fauré...2'21
6/Ave verum - Camille Saint-Saëns...6'24
7/Benedicat vobis Dominus - Henri Duparc ...3'54
8/Notre-Père - André Caplet...3'51
9/Je vous salue, Marie - André Caplet...1'47
10/Sous ton présidium - Guy Ropartz...2'08
11/ En prière - Gabriel Fauré...2'22
12/Puisqu'ici bas toute âme - Gabriel Fauré...3'06.
13/Le ruisseau - Gabriel Fauré...3'29
14/Madrigal - Gabriel Fauré...3'45
15/Pavane - Gabriel Fauré...4'55
16/La nuit - Ernest Chausson...3'00
17/Réveil - Ernest Chausson...4'21
18/L'hiver s'envole - Gabriel Pierné...2'43
モナコの小さな歌い手たち
子どもとフランスのメロディー:典礼から詩へ
監督: フィリップ&ピエール・デバット
1/Tantum ergo - ガブリエル・フォーレ
2/Ave verum - ガブリエル・フォーレ
3/ヘイル・レジーナ - ガブリエル・フォーレ
4/マリア・マーテルの感謝 - ガブリエル・フォーレ
5/アヴェ・マリア - ガブリエル・フォーレ
6/アヴェ・ヴェルム - カミーユ・サン=サーンス
7/ベネディカ・ヴォビス・ドミナス - アンリ・デュパルク
8/主の祈り - アンドレ・カプレ
9/メアリーより、ご挨拶 - アンドレ・カプレ
10/サブトゥム・プラシディウム - ガイ・ロパーツ
11/ 祈りの中で - ガブリエル・フォーレ
12/ここにすべての魂が宿っているから - ガブリエル・フォーレ
13/流れ - ガブリエル・フォーレ
14/マドリガル - ガブリエル・フォーレ
15/パヴァーヌ - ガブリエル・フォーレ
16/夜 - エルネスト・ショーソン
17/目覚まし時計 - エルネスト・ショーソン
18/冬は飛んで行く - ガブリエル・ピエルネ (Google翻訳)
ボーイ・ソプラノ Harmen Huigens ~ 天性のハイソプラノ ― 2025年12月18日 01時10分57秒

Harman Huigens jongenssopraan
清らかで伸びやかなソプラノが、ピアノやオルガン&オーボエ等と掛け合い溶けあい、曲を紡いでいくのが、心地良い。この濁りの全くない声が大聖堂に響くさまには、 スタンディングオベーションを受けたことだろう。ボーイソプラノが美しすぎる。解説にハイソプラノという表現があるが、ラクに高い音が出せるので、聴かせ所の高音域も普通に聞き流してしまいそうになるのがもったいない。【耳福(じふく)=耳で楽しむ幸せ】がここにある。
残念なのは、きれいな声だけでは歌えない選曲があったこと。人生経験を積まなければ歌えない曲がある。
Hetsuji欲で、この作品にもっと欲しいものがあるとすれば、Hetsuji的宗教観(神の存在)という個人的な感覚のみ。収録された曲は、一つ一つの音が、ひたすら麗しい。
by Hetsuji 2025.12.17 wed up
このCDには、彼が過去3年間のコンサートで歌った作品が収録されています。モテット「我が祈りを聞け」は、2000年4月28日にピーターバラの諸聖人教会の少年合唱団との共演によるコンサートのライブ録音です。「ラウダーテ・ドミヌム」は、シュターツクナペンコールの第2回ルストラム・コンサートでのライブ録音です。その他の録音は、1999年6月にアウデンボスの聖ルイ礼拝堂(1、3、4、7、9番)で、2000年3月にホリンヘムのルーテル教会(2、8、10、11、12番)で行われました。
合唱団の常任伴奏者のニコ・ブロム、オーボエ奏者のエルゼ・フェルミューレン、ボーイソプラノのセバスチャン・ファン・リンゲン(第2番)もこのCDに参加しています。 (by Google 翻訳)
少年合唱 Poznaner Knabenchor ~ 2003年9月1日より ― 2024年07月28日 20時51分42秒


1.Pasterze, pasterze
2.Pastuszkowie bracia mili
3.Dnia jednego o potnocy
4.Hola,hola pasterze z pola
5.Pastuskowie ze snu powstali
6.Nowy Rok blezy
7.Niech brzml chwala
8.A czemuz moj Jezu
9.Bracla, slostry postuchajcie
10.Dzieciatko sie narodzito
11.Z narodzenia Pana
12.Jezuz malusienki
13.Lulajze Jezuniu
14.W ziobie lezy
15.Aniot pasterzm mowit
16.Hej w Dzien Narodzenia
17.Bog sie rodzi
18.Pasterze mill
19.Triumfy
20.Witaj Jesu kochany
21.Sinfonia de Nativitate
ポズナン少年を含めて計5団体が参加している盤。
音が塊でしか聞こえてこない。どこか遠い。トレブルたちの声が口の中でこもっているように聴こえてくる。まるで採録用のマイクが歌っている人たちから遠く設置されているかのような音から醸し出される臨場感の不足がキビシイ。(私のお安いプレーヤーが原因かもしれないけれど-元々ソフトに再現されるプレーヤーなので)とにかくトレブルたちが遠すぎる。全体に大人しくきれいにまとめようとしていている。ようにも思える。大人の団体が活躍している盤とも言える。
ポズナンについては、1993年頃の鮮烈さはどこへ行ったのだろう? 少年の声を、演奏を、より引き立たせる採録技術の大切さを思い知らされる。
更に、各種録音からの寄せ集めCDの場合、音のレンジ?が広すぎて、ハッキリ聴こえない曲と、逆に音が大きすぎて、うっ!となる曲が入り乱れて、聴くのがつらい。それは、演奏を楽しむ以前の問題なのだが。
基本、私は外国語を理解しない。曲全体を把握する能力もない。なので、一つの音、音そのものの心地よさに注目して聴いている。こういう聴き方なので、私の感想は世間一般とズレているのかもしれない。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up)


1.Wsrod nocnej ciszy
2.Mizerna cicha
3.Cdy sie Chrystus rodzi
4.Dzisij w Betlrjem
5.Witaj Jezu ukochany
6.Badz pochwalon
7.Jezusek czuma
8.Nad stajenka gwiazda plonie
9.Chrystus Pan Sie narodzil
10.Zasnij Dziecino
11.Dzieci u zlobka
12.Dokad spiesza Krolowie
13.Pasli pasterze woly-Pasly sie owieczki
14.Nie bylo miejsca dla Ciebie
15.Do szopki hej pasterze
16.Spiewy jaselkowe
各種団体混合盤。 (MTJ CD 10007)よりも、採録された音は明瞭になっている。指揮者名にStefan Stuligrosz氏のお名もあり。でも、音は口の中で濁っている。ように聴こえる。
お国の作曲者盤? 曲調は非常に静かで寂しくて情緒的。肥沃な大地。なのに、かなしい感じがするのは、ポーランドの歴史故か? 盤の中では、やはり3-7,13-15のポズナン少年が情緒的だけれど、流され過ぎずに良かったと思う。13番目の曲の一声ソリストくんたちの声も盤全体のアクセントになっていた。
16番目はナレーションと歌の音楽劇。表示は18分だけど実際は時間オーバーしていた。テノールとかバリトンとか、男声合唱団とか。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up)

1.St.Nicholas
2.Omnis mundus iocuundetur
3.Hort zu ihr lieben Leute
4.In dulci iubilo
5.Woul mir, dass ich Jesus habe
6.Ave Maria treble solo
7.Alleluia
8.Mary's Lullaby
9.Torches
10.Krolu Anielski
11.Za gwiazda
12.Gdy sliczna panna
13.Lulajze Jezuniu
14.Gdy sie Chrystus rodzi
15.A czemuz moj Jesus
16.Pasli pastyrze woly
17.Pasty sie owiecki
18.Jesus malusienki
19.Tedy pozenem
20.O Tannenbaum
21.Stille Nachht
22.Ihr Kinderlein kommet
23.Still, still, still
24.Wiegenlied/Kolysanka
個性とか差別化はどうするんだろうと思った。上手な部類に入るのだろうけれど、指揮者が変わると音も変わる。ポルスキー時代とは違う。他の上手な合唱団(来日した有名所が国内にある)とどこが違うのだろう?
私にとってのポルスキー時代の魅力と印象は、キラキラした圧倒的なボーイ・ソプラノだった。が、ポズナンに変わってからのトレブルは、慎ましやかで大人しい。ただ音のバランスが変わったので(ポルスキー時代よりも男声部の存在感が増しているような気がする)トレブルが出すぎたり煌びやかになったりしないほうが音楽的に似合っているのかもしれない。指揮者の方向性なのだろうと思う。合唱>ソリスト、だもんね。
だが新生ポズナンは、男声部がとにかくとにかく麗しいのだ!まるでボーイソプラノの味わいそのままに、清冽冷涼なテイストそのままに、音の位置が低い方へ移動した感じなのだ。音の美しさに感動する。そこに偶然にトレブルのある種の音がハマればこのうえなく美々しく曲が仕上がる。そんな感じ。今のところ、課題は、トレブルの持って行き方、だと思う。木管系トレブルの良さは選曲で活かせるんじゃないか。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up)

1.Stabat Mater
Missa 1956
2.Kyrie
3.Gloria
4.Credo
5.Sanctus
6.Apnus Dei
1956年6月28日のポズナン暴動の死傷者100名超への追悼のミサでしょうか。最初は穏便なデモだったのが政府の介入で暴動に発展したのだそうです。
まずは、1.Stabat Materが、ソロも合唱も素晴らしいです。曲もどこか不安を掻き立てるメロディラインです。合唱団もソリストも外部から招聘されていて、ポズナンの存在感はありません。あ、高音部の合唱が(わたし的に)汚い音かも。初めて聴くスタバトですが、迫力があります。民族?的な表現かも。特にソプラノが。
ミサは、打楽器と管楽器の相乗効果で、これほどキリエっぽくないキリエもないです。祈りというよりは、抗戦的?な戦闘音楽みたいです。政府に制圧されるデモ隊の気持ちですかね。どちらも国民なのですが。ソプラノソロが、どこかアジアの音楽みたいです。唸るように歌っています。苦しみなのかな。恨みなのかな。インパクト大です。
でもずっとめんどり系ソロで、ちょっと疲れるかも。6.Apnus Deiでようやくポズナンが聴こえてくる。亡くなった方々と同時に、遺された方々の悲しみや怒りや憤りを慰めるのだろうな。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up)
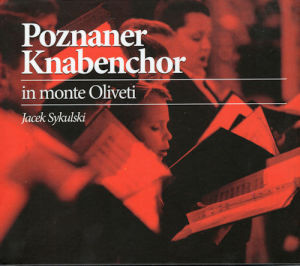

1.Cristobal de Morales-Parce mihi
2.Anonim (arr. Michael McGlynn)-Maria, matrem virginem
3.Anonim-Angelus ad virginem
4.Anonim-Riu, riu chiu
5.Tomas de Torrejon y Velasco-A este sol peregrino
6.J.David Moore-Annua Gaudia
7.Tomaso Lodovico da Vittoria-O magnum misterium
8.Waclaw z Szamotul-Juz sie zmiercha
9.Waclaw z Szamotul-Alleluja chwaice Pana
10.Barthomiej Pekiel-Magnum nomen Domini
11.Mikolaj Zielenski-Viderunt omnes
12.Mikolaj Zielenski-In monte Oliveti
13.Mikolaj Zielenski-Iustus ut palma florebit
14.Mikolaj Zielenski-Desiderium anime eius
15.Mikolaj Zielenski-Deus enim firmavit orbem terrae
16.Mikolaj Zielenski-Anima nostra sicut passer
17.Johann Sebastian Bach-Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225; Fuge
18.Leonhart Schroter-In dolci iubilo
19.Jacek Sykulski-The Peace Meditation
お兄さんChoir中心で麗しい。こういう感じの落ち着いた音作りが好きなんだろうな。
ぼーっと聴き流していて、あ、良いなーと思って曲順をみたらタイトルにもなっている 12.Mikolaj Zielenski-In monte Oliveti(オリーブ山にて)でした。
ポズナンはどちらかというと癖みたいなものが抜けて西欧的に洗練されてきているのだろうと思います。音配分のバランスも申し分ないですし。トレブルの音の感じは私の好みじゃないけど。
一定レベル以上の上手な合唱団ですよ。だけど思う。私が極東日本でこの合唱団を聴く意味はなに? って。私は、上手だからではなくて、心が動かされる録音を聴きたいんだもん。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up)

1.ROTA
2.MARSYLIANKA WIELKOPOLSKA
WOLNOSCI DLA NAS IDZIE CZAS
3.Postludium. Taka mi jestes ...
4.Kondukt Franciszka Ratajczaka
5.Batalia
6.Po moich ojcach...
7.Rota. Dzieci rodzicow...
曲の内容がわからないのですが、PC翻訳をアテにするなら「多くの時間を要して自由を得る」みたいです。
大陸で国境があり、隣国とリアルにせめぎあったり、大国や強国から侵入や支配を受けた国は、自由の重さが違うのでしょう。ポーランドはときに理不尽に踏みにじられてきた歴史がありますよね。それが忍耐強かったり民族的だったり・・・音楽にも投影されるんでしょう。
鷲の紋章はポーランドの国章のようです。1919年に王冠を載せた白鷲が国章に定められ、戦後は王冠を外しましたが1989年に国の体制が変わったことで再度、王冠が戻ったようです。ですがこの盤のカバーで無冠なのは、「まだ自由ではない」という主張でしょうか。この曲では、まだ自由じゃないみたいですよ。
表面上は静かだけれど、実は抑圧された民衆の激しいエネルギーがマグマのように深い地底でドロドロしているような曲で、聴いていて重いです。ホントのところは知らないので、的外れの感想かもしれません。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up)

u Pana Boga (MTJ CD 10918)
1.Domine
2.Luli Luli Lei
3.Stabat Mater
4.Zwiastowal Aniol Swiety
5.Ave Maria
6.Spij Synku Moj
7.Alleluja
8.Pastoralka
9.Agnus Dei
10.Czarowna Noc
11.Gloria
12.Proboszez
u Pana Boga は「神とともに」w ogrodku は「庭で」です。ポドラシェ県を舞台にした映画のようです。検索するとちょっと見れます。司祭さんが好演らしいです。
やはり私はトレブルさんたちの合唱の高音部が苦手です。どうにかならないかな。気にし過ぎかな。気になるトレブルさんたちも居るんですけど。貪欲になれないのは、今の私が疲れちゃっているからかも、ですね。ソロ・トレブルさんたちが気にいったのは5.Ave Mariaでした。初めて聴いた曲(作曲者)でしたが。11.Gloriaのトレブルさんも魅力的。映画の美しい風景にこの音楽が乗ったら素晴らしいと思います。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up)

MESJASZ
1.Sinfony
2.And the glory of the Lord
3.And the shall purify the sons of Levi
4.For unto us a child is born
5.Glory to God in the highest
6.His yoke is easy
7.Behold the Lamb of God
8.Surely he has borne our griefs ...
9.And with his stripes we are healed
10.And we like sheep have gone astray
11.He trusted in God that he would deliver him
12.Lift up your heads, O ye gates
13.The Lord gave the word
14.Let us break their bonds asunder
15.Hallelujah
16.Since by man came death
17.But thaanks be to God
18.Worthy is the Lamb
19.Amen
上手で聴きやすいのですが、突き抜けているわけではないので、普通に上手で、上手な合唱団の一つというイメージです。お手本みたいな演奏です。拍手が入ったのでライブですね。ライブとは思えないほど、整っていました。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up)

WEIHNACHT ORATORIUM
曲の完成度を上げるためなのか外部ソリストを招聘している盤ですね。普通に上手です。ファンとしては、ゲスト無しでお願いしたいところです。ポズナン、歌っていますか状態です。
世間的にも評価される、より良い作品を作り出したい気持ちは尊重したいですが、誰に向かって作っているのだろうか? と問いたいです。
ポズナン目当てにCDを買うのはポズナンをひいきするファンなんです。そこを覚えておいて欲しい。とはいえ、これもライブだわー。ソリスト外部招聘で納得。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up)

1.Prologus
2.Mesco
3.Dubravka
4.Baptisma
5.Crux
6.Regnum Poloniae
7.Nox et lumen
8.Epilogus Jozef Bieganski (boy soprano)
ホントかどうか、責任はとれないケド、966というのは、ポーランド公国として建国された年のようです。なので建国記念のオラトリオみたいです。
ポズナニ事件にしろ、建国記念にしろ、ポーランドの国史に対して、新生合唱団は、意欲的に取り組んでいるようにも見えます。国内でテッペン取ろうとしているのかな?
さてこの盤にはトレブルくんの名前が記載されていましたので転記しました。外部ソリストに混じってトレブルくんの声が収録されているのは有難いです。
外部招聘=ライブが約束ですが、オーケストラも含めてかなりの迫力です。これ歌舞伎だったりしたら、所作も付くんだろうな、と聴いていました。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up)

1.Stoneczko juz gosi ztoty blask Wojciech P/Ksawery
2.Spij dziecinko Wojciech P /Wojciech W
3.Dorotka Franciszek
4.W lesie ciemno juz Wojciech P/Ksawery
5.Byt sobie krol Alexander
6.Idzie niebo Franciszek
7.Siwa chmurka Wojciech P/Wojciech W/Alexander
8.Aaa, kotki dwa Wojciech P/Ksawery
9.Bajka iskierki Franciszek
10.Piosenka na dobrq noc Dominik
11.Spij, mojee ksiqzatko, spij Wojciech P
12.Dobrej ocy i sza Wojciech P/Wojciech W

(後列左より Alexander, Jacek 先生, Ksawery)
(前列左より Franciszek, Wojciech P, Wojciech W)
とてもキュートなポズナン版ソングブック。本になっていて歌詞と、ソリスト君たちのカッコいい写真がそれぞれ掲載されています。
タイトルが「サメの子守歌」。なぜにサメなのかわかりませんが、こもり歌もトレブル君たちのソフトな声が限りなく優しい。全員の声のテイストがこもり歌向き。聞流していたときには、歌っているなーでしたが、向き合って聴いている今、曲も声も可愛すぎる。幸せ過ぎる。Jacek 先生の方向性が見えたような気がした。ほぼほぼ似たように声を均している。なんだったら、一人のソリストと表記しても通りそうな声。それほど雰囲気が似ている。見事なくらいに。
テノールのドミニクも声の傾向は同じ。ソフトテイストで声を作り、曲を作って行くんだろうな、と思った。とにかくソフト&スイートなソングブック。(by Hetsuji 2024.07.28 sun up)
最近のコメント