ヴォイス・オブ・エンジェルズ 少年合唱団の天使たち L'Or des Anges PHILIPPE REYPENS ― 2008年12月31日 08時59分26秒

ヴォイス・オブ・エンジェルズ 少年合唱団の天使たち L'Or des Anges PHILIPPE REYPENS (UPLINK ULD-410)
不運が続いた怒涛の2008年もきょうで終わり。
やれやれ、です。
さて、2008年のブログを何で締めようかと思っても何も思い浮かばなかったのでコレ。・・・すみません。
実はこのL'Or des Anges ですが、私は、おフランス語の映像をビデオにコピーしたものを1999年にCHOIR友だちから借りて見ていました。
まだ国内で発売される前で、おフランス語のプロットみたいなものと、売り込み用みたいな出演団員くんのモノクロの写真(なんていうんでしたっけ? スチール写真?)5枚が同封されていました。
最後にお花を拾う意味、少年たちの後姿とお花がクローズアップされる意味とか、そこに込められた意図とかを、ビデオを貸してくれたCHOIR友だちから聞かされたものです。(忘れましたけれど)
資料はあったものの、何が描かれているのか解らない状態で、受け止め方は、そのとき、かなり自己流でしたね。
当時、繰返してみていたために、ビデオが発売された頃には飽きてしまってきっかけも無く、購入が今日に至ってしまいました。
で10年ぶりくらいに見て、受けた印象がなんだか違う・・・。
斜め読みですが、今回、日本語字幕付きで見ていると、ここに描かれている世界に住む少年たち(スタッフとしての合唱団に関わる大人たちもですが)は、「伝統」という宮殿の中の常置品みたいなもの、に感じました。
なんだか日常からは遠く、生きている「歴史」みたいなもの。
人が伝統や行事を重んじ、忘れることがないように、どこかでは大切に保存し、伝えていくだろうけれど、「遺物」に近い描かれ方で、彼らの存在からは、現在を生き生きと生きているという「生命力」を感じることが出来ませんでした。
PHILIPPE REYPENS氏は、これで「少年合唱団」を終わりにするつもりなんでしょうか?
未来への展望はないのでしょうか?
私はあると思います。
人はいつ歌いたいのか、なぜ歌いたいのか、最初に音を発する瞬間の思いを捉えるとき、きっと、答えがあります。
ぜひ、第2部を作って欲しい。
もしかしたら、それは、ヴォイス・オブ・エンジェルズではなくて、ヴォイス・オブ・ボーイズにタイトルが変わってしまうかもしれないけれど。
(そのとき、今回の映像でときどき感じた不思議な色っぽさみたいなものは消えているでしょう。)
「微熱」と「リジョイス」は初めて見ました。
このDVDのカバー少年とチューリヒ(かな?)の制服にL'Or des Anges では見覚えが無かったけれど、映画「微熱」の少年なんですね。
Polskie Slowikiを知ったのも、この映画と前後して、だったと思います。それまではCDを聴いていてもPoznanskie Slowikiと混同していました。
・・・にしても、感心したのは、団員くんたちが指導者の指導に応えて歌い方を変えていくシーンで、つくづくプロだなあと思いました。
どの世界でも、極めている方々というのは、大人子どもに関係なくスゴイもんです。
ブランジバールで歌っている二人(全員上手ですけれど)も良いですね。
一番、私が好きだったのは「リジョイス」かな。
Polskie Slowikiのデニスくんも収録されているし、思いがけなくフロリアンも。(新しい方の制服ですが)
割愛映像ではなくて、「合唱際」そのものの記録を見てみたい(聴いてみたい)です。
デニス君ももうちょっと前の声で聴いてみたかったな。
Polskie Slowiki ポーランド少年合唱団 The Polish Nightingales ~ 1999年に私が一番好きだった少年合唱団 ― 2008年12月31日 10時50分13秒
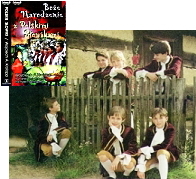
Boze Narodzenie z Polskimi Slowikami(Selene MC-397)
1999年にCHOIR友だちからカセットを何本か借りて聴いて(本も借りた)、この合唱団の魅力に取り付かれた。
残念ながら、すばらしかったボーイ・ソプラノたちのカセットは入手出来ず終い。CD以前(デニス君以前)の録音もまた、この合唱団は華やいでいた。
このカセット、A面とB面では、雰囲気がガラッと変わる。
それでいて、違和感が全くない。
A面は、おそらくお国の作曲家。
メロディは美しいが、初めて聴く曲ばかりで、緊張してしまう。
何度も繰り返すが、私たち(私)は、なんと偏って、ある一部の作曲家の曲ばかりを聴いていることだろう?
だからB面出だしのブラームスで、相当にほっとする。
B面は、台詞や歓声?入りの、特にB-Sソロの曲がほとんどポップス系のノリ。
とてもクラシック系には聞こえない。
かと思うと、別れの曲?の合唱も聴かせる。
おそらく、芸達者くんたちが各地でのコンサートのアンコールでこういう曲を披露しているんだろうと想像できる。
合唱に比較して、ここでのソリストたちはバリバリの完璧系ではないが、ときに超自然で超ぶっきらぼうな歌い方に幼さと、逆に聴かせようとしているときには、相当な芸人根性としたたかさを見る。
彼らは、一人一人がステージ上で聴衆を楽しませる術を身につけているエンターティナーのようだ。別なCDで宗教曲を歌っているときとは全く違う。
まるで無造作に、一人一人の力量に任せきったソロで、潔いほどに勢いと自由があって、そこがなんともいえない魅力になっている。
演奏のコピー・・・録っておくんだった~。カセットの画像も。
最近のコメント