Knabenchor der St. Willibrords-Kirche, Amsterdam アムステルダム聖ウィリブロード教会少年合唱団 ~ マタイ 肉の悲哀、愚かさ ― 2008年11月29日 08時29分35秒

J.S.Bach /マタイ受難曲 BWV244-ハイライト/オイゲン・ヨッフム指揮アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団、他(PHILIPS FG-5018 412 650-1) Recording Dates and Place: 1965.11.20-30, Amsterdam,Concertgebouw Timings
オランダ放送合唱団(合唱指揮:カレル・ロート)/アムステルダム聖ウィリブロード教会少年合唱団(合唱指揮:トーン・フランケン)/アグネス・ギーベル(ソプラノ=第33、77曲)/マルガ・ヘフゲン(アルト:第33、36、77曲)/ヨン・ファン・ケステレン(テノール=第77曲)/フランツ・クラス(バス=第77曲)/アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団/指揮:オイゲン・ヨッフム
私にとって基準の演奏がこれ!と言えるほどマタイを聞き込んでいないのだが、これも良いのではないだろうか?
歌声がろうろうと流れて緊迫感には欠けるような気もするが、緊迫感がマタイに必要かどうかも私にはわからないし。
私は女声が混じる合唱は苦手だが、マタイは別である。
所詮は地に縛られる人間の悲哀や愚かさやいわゆる人間そのものの肉としての存在の俗的な要素は女声と男声との混声の方がより表現され得ると思うから。そういうものが吹き出してくる序盤に、途中から遅れて聞こえてくるアムステルダム聖ウィリブロード教会少年合唱団の歌声は清冽で少年の声の面目躍如たるものを感じる。
The boys' choir "Zanglust" ツァンクルスト少年合唱団 ~ 聴衆のすすり泣き入りのマタイ ― 2008年11月29日 08時37分32秒
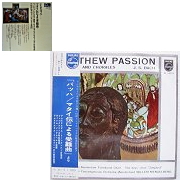
J.S.バッハ マタイ伝による受難曲-抜粋(fontana FG-250 MONO フォンタナ・レコード 発売元:日本フォノグラム株式会社) 1939年アムステルダムで録音。1974年発売。
カール・エルプ(福音史家)、ウィレム・ラヴェルリ(キリスト)、ジョー・ヴィンセント(ソプラノ)、イローナ・ドゥリゴ(アルト)、ロウイス・ファン・トゥルデル(テノール)、ヘルマン・シャイ(バス)、アムステルダム・トーンクンスト合唱団、ツァンクルスト少年合唱団(The boys' choir "Zanglust")、ウィレム・メンゲルベルク指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団
これは、第2次世界大戦が始まる年、1939年の棕櫚の日曜日(復活祭直前の日曜日)に、アムステルダム・コンセルトヘボウで行われた演奏会の実況録音である。
2時間余りの演奏を1時間程度に編集した馬場健氏の解説によると、このレコードは、名高いアリアやコラール等をつなぎ合わせるという普通のハイライト盤的編集方法を避け、作品のいくつかのクライマックスを中心に、場面ごとの物語的音楽的一貫性を大切にしたそうだ。
この演奏会では、まさに戦争直前の時代的な暗さの中に精神が張りつめていた聴衆が、キリストを磔にした過去の民衆の行為をあたかも自分がかつて実際にそうしてしまったかのように悔い、或いは自分自身が理解されずにこれから磔になるキリストであるかのように、聴きながら泣いている声も入っている。
約30年前に聴衆のすすり泣き入りのマタイが存在していることは噂では知っていたが、感動する演奏会だったんだろう位に単純にしかとらえていなかった自分自身の浅はかさを恥じ、実際に聴いてみて、すすり泣きの意味の違いに気がつき、愕然とした。
人間というのはちっぽけな存在なのに何故こんなにも愚かで2000年以上も前から魂が進歩しないんだろう?
昔の実況録音は、現代の全てが平面上にクリアに聞こえるCDと違い、湿った黒砂糖の塊みたいに大きくごつごつしていて細部の音がファジーにかすんでとんでしまうのが惜しい。
けれども、そこを差し引いてもこの演奏は、群衆の合唱にも、静かなコラールにも聴いていて心が動く。
ソリストも合唱団もその経歴を私は知らないが歌い方に癖がなくて聴きやすい。
だが、このマタイは実際の演奏者・プラス演奏に感応した会場の聴衆、何よりもそういう状況に追い込んだ「時代」が創った特異なマタイだ。
バッハ:マタイ伝による受難曲」より(PHILIPS FL-4511) 1939年の棕櫚の日曜日、アムステルダム・コンセルトヘボウに於ける歴史的録音。
上の盤の抜粋。
何年にプレスされたものかわからないが、このレコードの値段は1000円。この値段、この選曲を見て、いったい当時、どのような客層が聴いたのだろうと思った。日本にも富裕な方々がおられたのだな。
かつての私の生活にはほど遠い存在だったこの手のレコードを聴くことができる時代になったことを感謝。
63番、78番あたりで、お~マタイ・・・と実感する程度のリスナーではあるが。
抜粋盤というのは、全曲を聴いたことがあるもののためにあるのではないかとふと思った。ああこの曲、聴いた聴いた、とは思うのだが、抜粋は決して作品そのものではないから大曲の場合、良さは伝わりにくい。
この点がミュージカルの抜粋とは違う。ミュージカルなら作品の中の、有名曲数曲でなんとなく満足したり出来る。
不思議なものだ。
こびとかば 様へ ― 2008年11月29日 09時27分01秒

いつも、素晴らしいコメントをどうもありがとうございます。
こびとかば様の音楽への感じ方にいつも触発されています。
こびとかば様の
ウィーン少年合唱団のカンタータ
Johann Sebastian Bach KANTATEN (SAWT 9539.B)
197番のソリストや
マタイについてのお話等
そ~だ~とか嬉しくて
ついつい
数年前に書いていたマタイレコードへの感想文を
アップしたのですが
こびとかば様の最新のコメントを公開して
いざ
お返事を、
と思っていたのですが、
・・・・・・こびとかば様のコメントを公開する操作を誤って
私とこのブログにとって大変貴重なコメントを
消してしまいました。
・・・・・う・う・う・う・う・・・・・・・・・。
申し訳ありませんでした。
これに懲りて
私を見捨てないで下さい。
これからもいろいろと
教えてください。
ライプツィヒ聖トーマス教会合唱団 THOMANERCHOR LEIPZIG ~ 王道中の王道の合唱 ― 2008年11月29日 22時04分29秒

JOHANN SEBASTIAN BACH:KANTATEN BWV 18 UND 62 (ARCHIV PRODUKTION 198 441)
Recording: Leipzig, Hans Auensee, 28.-30.(31.)November 1967
Dirigent:Erhard Mauersberger
ここでは第18番《天より雨くだり雪おちて》BWV18 Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel falltと、第62番《いざ来ませ、異邦人の救い主》ⅡBWV62 Nun komm, der Heiden Heilandが取り上げられている。
この二つが何故とりあげられたのかは外国語文盲故に不明。異教徒には計り知れない意味があるのかもしれぬ。
バッハのカンタータシリーズの対訳を引っ張り出して聴いた。
あの有名なシリーズと比較するとこちらの作品の方が溌剌として威勢がよいような気もする。けれど少年合唱ファンのバイブル(?)でもあるあのシリーズが世に出てしまったからなあ・・・。
それから、もう一つ、気が付いたことがある。トーマス教会の合唱は、全体に張りがあって、67年の録音であるが、時代による古さを全く感じさせない。
どうしてもソプラノやテノール等大人のソリストが目立ってしまって、どちらかといえば合唱の印象が薄いのだが、私の耳には、少年声の音質が理想的な色彩と温度をもって聞こえた。
この録音では、男声部は研鑽の余地有りと感じたが、こと少年声部に関しては魅力を感じた。
この時代のドイツの3高峰、レーゲンスのどこか希薄なこの世のものとは思えない木漏れ日のようなやさしさやわらかさ、クロイツの堅固な内にもろさ、もろさの内に強さを秘めた風雅に鄙びた合唱を味わうにはレコードに限る。
が、このトーマナの合唱は王道中の王道、いわば枝葉をそぎ落とした幹だけの趣があり、時代に左右されない「合唱」の基本姿勢のようなものを感じる。
最近のコメント